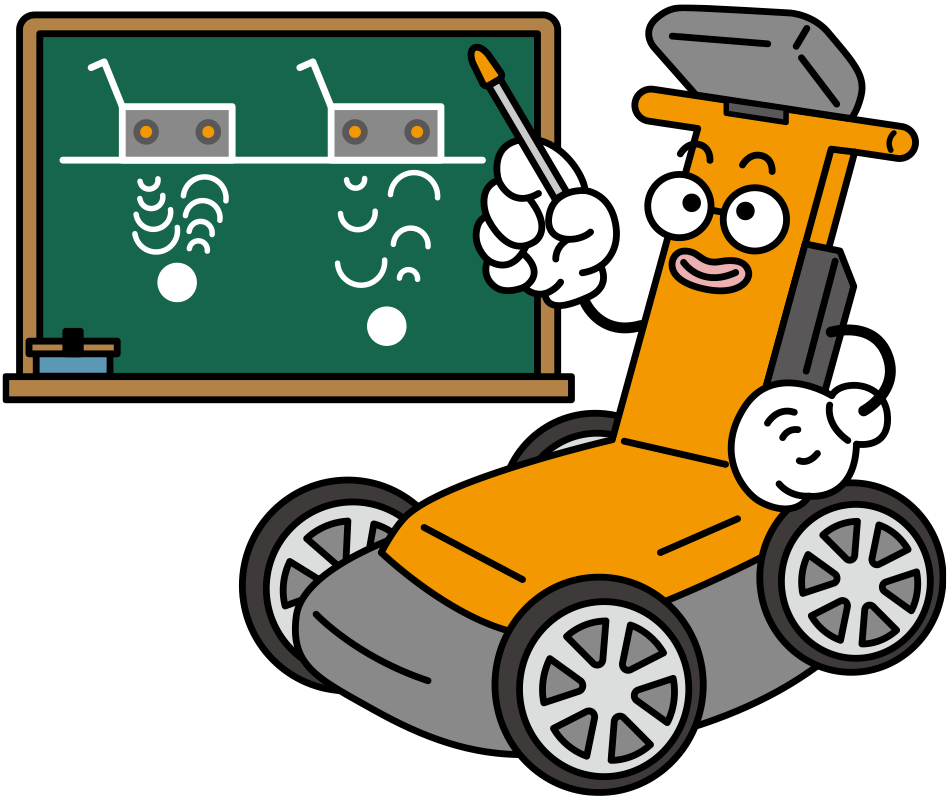舗装厚調査
道路工事が繰り返されると、道路の舗装厚が変化します。
舗装厚のゆがみを放置すると陥没事故やひび割れの原因となるため、定期的に道路調査を実施する必要があります。
もっとも効率的に調査できるのが、地中レーダを使った非破壊連続探査。舗装面を連続的に探査することによって、表層の厚みや状態はもちろん、路盤内部に生じたダメージまで検出することが可能となり、交通インフラの維持管理を効果的に行うことができます。
そこで本ページでは、舗装厚調査の依頼先の選び方からおすすめの会社まで詳しく紹介します。 道路陥没事故など、重大な事故に繋がる前に、信頼できる会社に調査を依頼しましょう。
舗装厚調査に求められる条件
舗装厚調査は浅い箇所の計測であることから、浅深度帯をクリアに計測できる1,000MHz以上の高周波帯地中レーダを使用することが推奨されています。
さらに、長距離の道路や橋梁を計測する必要があるため、車載式地中レーダであれば効率的に実施できるでしょう。
舗装厚調査の概要
レーダ探査のメリット
地中レーダ探査は、電磁波の性質を利用して、路面下の状況を把握する探査技術です。放射波と反射波の伝播時間を取得することで、舗装構造物を破壊することなく、正確かつ迅速に把握できます。
電磁気的な物性境界面で反射するのは電磁波の持つ特性です。電磁波をコンクリート面に向けて放射すると、性質の異なる物質の境界面で反射され、コンクリート表面に出てアンテナが受信します。送信から受信までの時間から反射物体までの距離が把握可能です。
レーダ探査の一番のメリットは、舗装表面を破壊する必要がないことでしょう。開削工事と比較して、調査時間とコストを大幅に削減できることはもちろん、利用上の不便も回避できます。また、調査対象物の材質に関わらず探査ができること、機動性が高いこと、広範囲を効率よく探査できることもメリットです。
レーダ探査の測定手法
レーダ探査の方法には、パルス方式とステップ周波数方式があります。従来はパルス方式でした。パルス方式では、調査目的に応じた周波数アンテナを使用して調査を行う必要がありましたが、ステップ周波数方式の「三次元地中レーダ」では、200MHz 〜3GHzの周波数に対応していて、周波数を段階的に上げながら調査できます。
レーダ探査の測定原理
電磁波の反射を利用して、舗装構成材料の境界面を捉える技術であることは上記で説明した通りです。各層の厚さ(D)は、「D=(1/2)×T×V=(1/2)×T×(3×108/√ε」で求められます。反射時間がT、比誘電率がε、電磁波の速度(m/s)はV、そして表面から境界面までの厚さ(m)がDです。反射時間と比誘電率がパラメータとなっています。
比誘電率の一覧を参考に提示します。比誘電率とは、対象となる材質の誘電率と真空誘電率の比のことです。
- 空気:比誘電率1
- コンクリート:比誘電率4~12
- アスファルト混合物:比誘電率4~6
レーダ探査機から電磁波を放射して、電磁的な物性境界面で反射されて返ってきた反応から、厚みを計測するのが舗装厚調査におけるレーダ探査機の仕組みです。
レーダ探査の活用例
舗装厚調査は、レーダ探査の活用例のひとつです。例えば橋面舗装補修工事にあたり、既設のアスファルト舗装を切削する場合、床版上面を傷つけないよう事前に既設アスファルト舗装の厚さを把握する必要があります。これまでは、コアを採取して対応してきた現状がありますが、限られた時間内では作業範囲や数量ともに制約を受けてしまうことから、既設舗装厚を簡単に把握することはできません。そこで活用できるのがレーダ探査です。アスファルト混合物の比誘電率から簡素に既設舗装厚の把握・確認ができます。
日本道路株式会社 技術研究所の資料では、室内試験でアスファルト混合物層の比誘電率の確認をおこなった上で、実橋での既設舗装厚と比較。事前にキャリブレーションを行うことで床版の種類によらず既設舗装厚を適切に推定できるというレーダ探査機の適用性評価が導き出されています。
ボーリングによるコア採取
ボーリング調査のメリット・デメリット
コア採取に活用する現代のボーリングマシンに関しては小型でクローラを装備していることによって、マシンの設置や撤去にかかる時間を短縮しやすくなっており、移動作業についてもスムーズに行えることがポイントです。これにより現地での作業時間を圧縮して交通渋滞や交通事故のリスクを低減できます。反面、コアの一部が掘削の振動で圧縮され、体積が減少するなど舗装構造の正確な厚さを確定できない場合があることはデメリットでしょう。
ボーリング調査の測定手法
ボーリング調査では作業後の舗装段差を発生させないことを前提として、交通事故や交通渋滞に配慮しつつ、交通量や気候・天候といった諸条件に関しても考慮した上で安全管理を徹底して行います。
具体的な測定としては検査地点へボーリングマシンを設置し、ボーリングによってコアを採取して、また孔内カメラを使って道路内部の状況を撮影・観察することもポイントです。
なお検査後はボーリングによって空いた穴を塞ぎ、舗装段差が生じないように整えます。
ボーリング調査の活用例
実際のボーリング調査の活用例としては、例えば幹線道路において舗装工性を把握し、道路の破損の原因や補修作業の必要性をチェックして作業対象となる区間を決定する場合などが挙げられます。
またボーリングマシンを使った調査だけでは採取コアの影響による不足も考えられるため、孔内カメラといった機器を利用して作業品質を高めるといった方法もあるでしょう。
舗装厚調査に対応する建設コンサルティング会社の選び方
舗装厚調査の対象となる道路延長は長距離に及ぶため、膨大なデータを迅速に処理する能力を有し、必要箇所の精査にも対応していることが求められます。
地中レーダを用いた探査は歴史が浅く、対応可能な会社が少ないことが現状です。
依頼する際は、信用できる会社に依頼するようにしましょう。
本ページでは、以下3つの条件が公式HPに記載されている会社の中から、舗装厚調査に適した特徴を持つ会社を紹介しています。
- 車載式地中レーダを保有
- 地中レーダ探査の実績保有
- 技術士・RCCMなどの資格保有者在籍
【特徴別】舗装厚調査に対応する
建設コンサルティング会社3選
2022/4/20時点Googleにて「地中レーダ探査」「舗装厚調査」と検索して表示された会社のうち、舗装厚調査に対応している建設コンサルティング会社を調査。調査に適した会社として、「車載式・ハンディ式地中レーダ両方を保有」「地中レーダ探査の実績保有」「技術士・RCCMなどの資格保有者在籍」を満たした会社のから舗装厚調査において下記のような特徴のある3社を紹介しています。
カナン・ジオリサーチ・・・唯一地上の360°情報の取得が可能な地中レーダを保有
ジオ・サーチ・・・公式HPに実績数日本一の記載あり
応用地質・・・唯一AIによるデータ分析が可能
カナン・ジオリサーチ
工数・コスト削減を実現


https://canaan-geo.jp/
カナン・ジオリサーチの特徴
異常箇所の位置特定における工数削減が可能
カナン・ジオリサーチは、自社開発した地中レーダ「GMS3 地中レーダ3次元モバイルマッピングシステム」を保有。3軸方向からの計測が可能な地中レーダシステムと、地上が全方位確認可能なモバイルマッピングシステムを、GPS時刻で同期させながら探査を行います。
舗装厚に異常が検出された際、同時に地上の状況をオルソ画像にて確認が可能なため、場所の特定における工数が大幅に削減され、後の補修工事を大幅に時間短縮します。それにより、交通規制の時間も短縮されるなど、工数・コスト削減につながります。
探査データを道路管理台帳
として活用可能
カナン・ジオリサーチは、自社で開発した地中レーダ「GMS3」の専用GISソフト「GMS3ビューア」を保有。取得した地下情報と地上のオルソ画像を1画面で同時に閲覧できるため、常に異常箇所直上の状況を確認することが可能です。
また、地上データは公共測量作業規定に定められた1/500精度での出力が可能。計測データを道路管理台帳としても利用できるため、道路管理の適正化にも役立ちます。
カナン・ジオリサーチの
舗装厚調査事例
カナン・ジオリサーチの舗装厚調査の事例は公式HPに掲載はありませんでした。
他の地中レーダ探査事例は下記リンクからご確認ください。
カナン・ジオリサーチの保有製品例
(トラックタイプ)

- 形状
- 車載式
- 周波数
- 3GHz~200MHz
- チャンネル数
- マルチチャンネル
- レーダ出⼒⽅式
- ステップ周波数
- 探査可能幅
- 2.1m程度
(複数走行により網羅) - 探査可能速度
- 80km/h
(車載タイプ)

- 形状
- 車載式
- 周波数
- 3GHz~200MHz
- チャンネル数
- マルチチャンネル
- レーダ出⼒⽅式
- ステップ周波数
- 探査可能幅
- 1.6m
(複数走行により網羅) - 探査可能速度
- 80km/h
(軽自動車タイプ)

- 形状
- 車載式
- 周波数
- 3GHz~200MHz
- チャンネル数
- マルチチャンネル
- レーダ出⼒⽅式
- ステップ周波数
- 探査可能幅
- 0.9m
(複数走行により網羅) - 探査可能速度
- 80km/h
(カートタイプ)

- 形状
- カート式
- 周波数
- 3GHz~200MHz
- チャンネル数
- マルチチャンネル
- レーダ出⼒⽅式
- ステップ周波数
- 探査可能幅
- 0.9m
(複数走行により網羅) - 探査可能速度
- 記載なし
カナン・ジオリサーチの会社情報
| 所在地 | 愛媛県松山市今在家二丁目1番4号 |
|---|---|
| 受付時間/定休日 | 9:00〜18:00/土曜・日曜・祝日 |
| 電話番号 | 089-993-6711 |
| 公式HP URL | https://canaan-geo.jp |
ジオ・サーチ
世界トップクラスの実績※
ジオ・サーチの特徴
地球6周分以上に相当する
距離を計測※
1989年に創業したジオ・サーチが調査した道路延長は、2022年3月末現在で257,472km。地球を6周以上した計算になります。 自社開発した地中レーダ「スケルカー」を31台保有しているため、計測距離に合わせて適切な製品での計測が可能です。
その対応力から、日本国内、韓国など、多くの感謝状を授与。路面下空洞調査、舗装厚調査をはじめ、多くの地中レーダ探査業務を請け負っています。
「計測技術コンペ」で
各市町村から高評価獲得
各地方自治体では、社会インフラ管理において入札時の価格競争激化を防ぐため、福岡市や大阪市などを中心に技術コンペ型の入札を実施しています。ジオ・サーチは、これらの技術コンペにおいて2位以下に大きく差をつけて優秀な成績を収め、高い評価を受けています。
多数の実績に基づく高い解析力を誇っており、国内外から地中レーダ探査業務の依頼を受けています。
ジオ・サーチの舗装厚調査事例
ジオ・サーチの舗装厚調査の事例は公式HPに掲載はありませんでした。
他の地中レーダ探査事例は下記リンクからご確認ください。
ジオ・サーチの保有製品例

画像引用元:ジオ・サーチ、公式HP(https://www.geosearch.co.jp/tech/)
| 形状 | 車載式 |
|---|---|
| 周波数 | 記載なし |
| チャンネル数 | 記載なし |
| レーダ出⼒⽅式 | 記載なし |
| 探査可能幅 | 記載なし |
| 探査可能速度 | 記載なし |
| 形状 | 車載式 |
|---|---|
| 周波数 | 記載なし |
| チャンネル数 | 記載なし |
| レーダ出⼒⽅式 | 記載なし |
| 探査可能幅 | 記載なし |
| 探査可能速度 | 記載なし |
| 形状 | 車載式 |
|---|---|
| 周波数 | 記載なし |
| チャンネル数 | 記載なし |
| レーダ出⼒⽅式 | 記載なし |
| 探査可能幅 | 記載なし |
| 探査可能速度 | 記載なし |
ジオ・サーチの会社情報
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7-37-10-9階 |
|---|---|
| 受付時間/定休日 | 公式HPに記載はありませんでした |
| 電話番号 | 03-5710-0200 |
| 公式HP URL | https://www.geosearch.co.jp/ |
応用地質
道路内部調査が可能


https://www.oyo.co.jp/
応用地質の特徴
時速80km/hで
2.5m幅の計測が可能
応用地質は、自社開発した車載式地中レーダ「ロードビジュアライザー」を使用して計測を実施しています。一度の走行で2.5mと広い幅を計測できるため、広域幅を詳細に計測できるほか、計測漏れを防ぐことが可能です。
さらに計測可能速度は最高80km/hのため、高速道路でも交通規制なしでの計測が可能。 比較的長距離計測が必要な舗装厚調査でも、効率的に計測することができます。
AIによる解析技術で
調査の品質を一定化
応用地質では、日立製作所と提携し、AIを使用した出力データの自動解析技術を先駆的に開発し、舗装厚調査に活用しています。AIを活用することによって、出力データの品質を一定化できるため、異常箇所の見落としを防ぐことが可能です。
またAIでの解析は、走行中に取得された膨大な測定データの解析をほぼリアルタイムで実施することが可能。長距離道路の計測でも解析時間を短縮することができます。
応用地質の舗装厚調査事例
応用地質の舗装厚調査の事例は公式HPに掲載はありませんでした。
他の地中レーダ探査事例は下記リンクからご確認ください。
応用地質の保有製品例

https://www.oyo.co.jp/services/infrastructure-maintenance/udevisuraiza-by-the-road-under-exploration/
- 形状
- 車載式
- 周波数
- 2,000MHz〜400MHz
- チャンネル数
- マルチチャンネル
- レーダ出⼒⽅式
- 記載なし
- 探査可能幅
- 2.5m
- 探査可能速度
- 80km/h

https://www.oyo.co.jp/services/infrastructure-maintenance/udevisuraiza-by-the-road-under-exploration/
- 形状
- 車載式
- 周波数
- 350MHz
- チャンネル数
- マルチチャンネル
- レーダ出⼒⽅式
- ステップ周波数
- 探査可能幅
- 記載なし
- 探査可能速度
- 記載なし

https://www.oyo.co.jp/services/infrastructure-maintenance/udevisuraiza-by-the-road-under-exploration/
- 形状
- 車載式
- 周波数
- 300MHz・800MHz
- チャンネル数
- マルチチャンネル
- レーダ出⼒⽅式
- ステップ周波数
- 探査可能幅
- 記載なし
- 探査可能速度
- 記載なし
応用地質の会社情報
| 所在地 | 東京都千代田区神田美土代町7番地 |
|---|---|
| 受付時間/定休日 | 9:00〜17:00/土曜・日曜・祝日 |
| 電話番号 | 03-5577-4501 |
| 公式HP URL | https://www.oyo.co.jp |
舗装厚調査の概要
舗装厚調査の計画
舗装厚調査の実施計画は、道路パトロールによる目視巡回の結果、舗装台帳及び道路台帳、補修等の工事履歴と、交通量や走行速度、渋滞といった交通条件、さらに気象条件その他の要素を総合し、調査計画を策定します。
一次調査
対象区域・路線の全舗装の状態把握を目的とした一次調査では、地中レーダによる連続非破壊探査、乗車・歩行による目視調査を実施。一次調査によって精査を要する箇所が特定されると、破損状況のアセスメントを目的とした二次調査が実施されます。二次調査
二次調査では、路面の状態や構造を精査します。路面調査として、路面のひび割れ状況、わだち掘れの測定、平坦性と現場透水量の測定、すべり抵抗、きめの深さの測定。構造調査としては、路面の弾性係数や路床支持力の測定に加え、コア採取と開削調査によって各層の状態や路床・路盤材の性状をチェックします。補修工事
詳細調査の結果を受け、損傷箇所に適切な補修を施します。また、発見された異常と補修作業の内容はできるだけ詳細に記録・蓄積し、将来の道路保全に活用します。
参照元:国土交通省道路局公式資料(PDF)(https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo28_10.pdf)
舗装工事の厚さ基準について
道路舗装はアスファルト舗装とセメントコンクリート舗装、コンポジット舗装などがありますが、例えばアスファルト舗装に関して見ても、舗装目的や工事内容によりアスファルト舗装の層の種類や厚さの基準が異なっている点は重要です。
歩道の場合
車の通行がなく歩行者が移動するために設けられている歩道の場合、表層の厚さは3~4cm、基層はその都度に条件に合わせて調整され、路盤は10cm程度を目安とされます。また自転車や車椅子といったものの交通量も考慮しなければなりません。
簡易舗装の場合
簡易舗装は基層を備えていない簡易的な構造による舗装道路を指します。表層は3~4cmですが条件によっては2.5cmなども可能となっており、路盤は15cm程度が目安となっています。
簡易舗装は小規模の駐車場や駐輪場、あるいは交通量が一定以下になっているケースなどにおいて利用されているタイプです。
一般道路の場合
一般道路は舗装道路としての耐久性や安定性が歩道や簡易舗装よりも求められるため、表層と基層において5~10cm程度、路盤は15~20cm程度が目安となるでしょう。
また交通量の多さなどに比例してそれぞれの厚さがさらに増加することもあります。
【PR】インフラの老朽化問題の解決のために開発された
3Dレーダ式地中レーダの活用レポート


https://digital-construction.jp/news/81
道路の老朽化に伴う補修工事の必要性は日本の大きな課題となっています。しかし、社会インフラ整備に使用できる予算の都合上、整備は主要道路のみに集中していることが現状です。
そんな課題のために開発されたのが、カナン・ジオリサーチが開発した地中レーダ「GMS3 地中レーダ3次元モバイルマッピングシステム」です。本ページでは、実際にGMS3を導入して地中レーダ探査を実施している企業にその効果をインタビューしました。