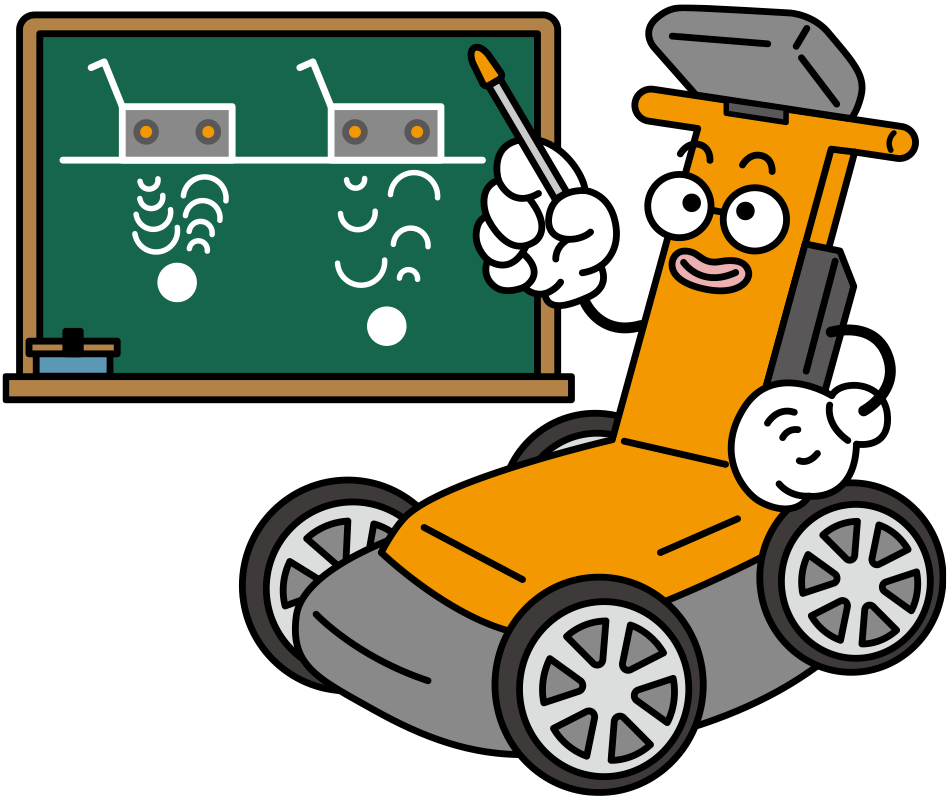地中レーダ探査(GPR探査)に関するQ&A
GPR探査(地中レーダ探査)とは
GPR探査のGPRとはGround Penetrating Radarの略。つまり地中レーダ探査のことで、地中の埋設物や地面の内部構造をマッピングするために電磁波を使ってその反射データから分析する手法のことを指します。
超音波を発射してその反射データから魚の群れを見つける魚群探知機と基本的な考え方は同じです。しかし地中の構造は複雑で物質により反射率が違ったり、深くて地中レーダの電磁波が届かなかったりすることもあります。
またGPR探査の目的はさまざまで、地中の埋設物だけでなく空洞探査や遺跡探査、地質調査などにも利用されます。そのためGPR探査では目的や用途に応じたレーダ装置が必要で、周波数や物質による違いも理解しておく必要があります。
そもそも地中レーダの原理って?
地中レーダが電磁波を発射すると地中の空洞や埋没物などの影響を受けた反射波が返ってきます。この反射波を計測することで地中の構造を把握するのが基本原理。そのため大がかりな装置やボーリング工事は必要としません。
また地中レーダはアンテナを移動させながら連続測定を行うプロファイル測定と、それで捉えた反射面に対して送受信間隔を変化させ、測定地点の地盤の電磁波速度を求めるワイドアングル測定の2通りの方法が用いられます。
地中レーダの周波数の違いは何が変わるの?
地中レーダが発信する電磁波は周波数によって特性が異なります。探査を行うためには周波数による違いを理解しておくことが必要です。周波数が低いほど計測可能な深度は深くなりますが、分解能は低くなり探査の精度は落ちてしまいます。
高精度と高分解能探査を実現するためには周波数を高くすればよいのですが、電磁波の減衰量が大きくなるため計測可能深度は浅くなります。また比誘電率は物質により違い、比誘電率が高いと高周波信号が流れにくくなります。
地中レーダの計測可能深度ってどれぐらい?
コンクリートの構造や地中の埋設物や空洞を調べるような一般的な地中レーダ探査の場合、深度限界は3~4mくらいです。地質調査などの場合は低周波地中レーダを使用し、最大探査深度5~10mを超える測定も可能です。
また計測可能深度は周波数だけでなく地中の物質に応じて変わります。これは物質の違いによる比誘電率が測定深度に影響するためで、同じ物質でも含水率が高くなると比誘電率も高くなり計測可能深度も変化します。
地中レーダ探査(GPR探査)に使われている電磁波とは?
地中レーダ探査に使われている電磁波とは、電場と磁場の変化を伝える波(波動)の総称です。電磁波を大きく分類すると、電波、光、X線・ガンマ線など。それぞれ波長が異なり、作用の性質も異なります。地中レーダ探査(GPR探査)とは、この電磁波の「波動」の性質を利用し、地中に放出した電磁波の反射波を測定して地下の構造を分析する調査です。
なお、一部の電磁波(X線やガンマ線など)には、人体や動物、機械などへの影響があるため、法律によって使用が規制されています。