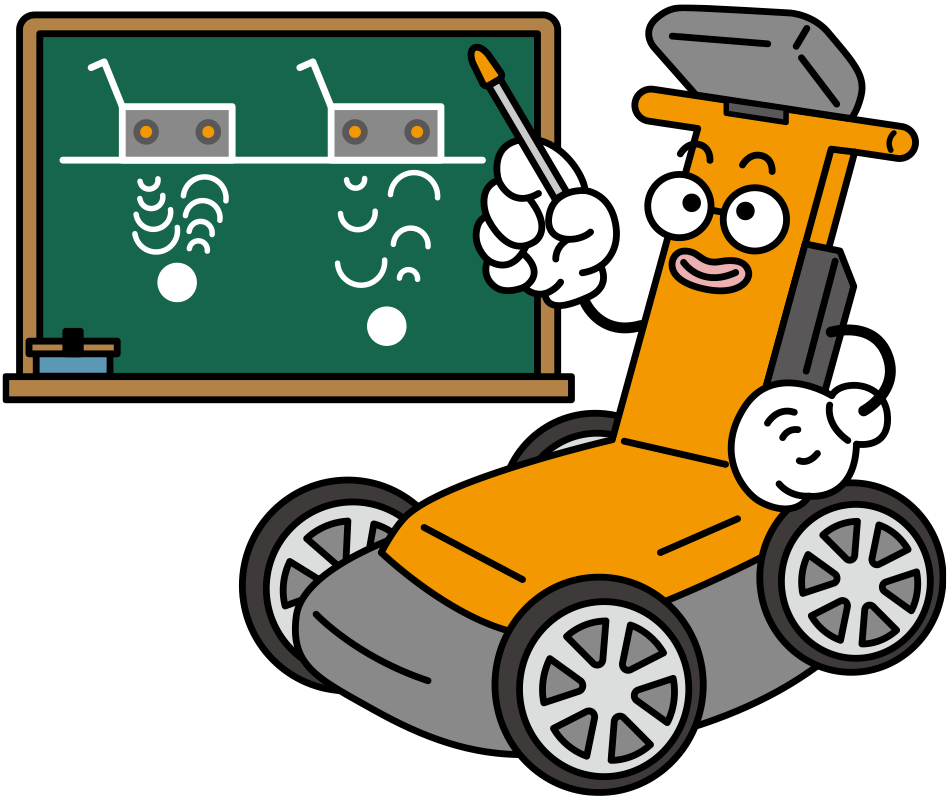地面下障害物調査
都市の再開発やインフラ整備の現場では、地下に埋設された水道管や電線、古い基礎杭、さらには天然の空洞などが掘削作業を思わぬトラブルに巻き込みます。
たとえば、近年発生した道路陥没事故では未検知の下水道管周辺に空洞が形成されていたことが判明し、その修復だけで多額の費用と大幅な工期遅延を招きました。こうしたリスクを未然に防ぐためには、非破壊かつ効率的に地中の状況を把握できる調査技術が不可欠です。事故を防ぐだけでなく、計画通りの工期やコストを確保するうえで、地中障害物調査は現代の建設現場にとって欠かせないステップになっています。
地面下障害物検知の主な手法
地中レーダー探査(GPR)の原理と特徴
地中レーダー探査は、地表に置いたアンテナから高周波の電磁波を地中に送り込み、埋設物や地層の境界で反射して戻ってきた信号を受信・解析する手法です。電磁波の周波数が高いほど細かい障害物を捉えやすく、低いほど深い位置まで届きます。一般的には200〜900MHz程度のアンテナが使われ、たとえば400MHzでは最大6mほど、900MHzだと1〜2m程度の深度探査が可能です。解析ソフトで断面画像をつくると、配管の走行や空洞の位置が可視化されるため、施工計画への反映もスムーズに進みます。
地中レーダ探査を行っている
建設コンサルティング会社
一覧を詳しく見る
電磁誘導法(EMI)の仕組みと活用例
電磁誘導法は送信コイルで磁界を作り、地中の金属埋設物に誘導電流を発生させ、その二次磁界を受信コイルで捉える仕組みです。歩きながら送受信器を移動させ、反応が強くなる地点で埋設物の位置を推定します。感度が高いため上下水道管やガス管など金属管の検出に優れ、調査時間やコストを抑えつつ広範囲をカバーできるのが特徴です。非金属製には反応しませんが、金属管のみをピンポイントで探したい場合に重宝されます。
磁気探査による鉄系埋設物の検出
磁気探査は、地中にある鋼製杭や不発弾といった強磁性体が地球磁場下で起こす微弱な磁気異常を測定する技術です。磁気勾配計やガウスメータを地表上で走査し、異常値を検出するとその地点に鉄製埋設物があると判断します。舗装や地形の影響を受けにくいため、道路工事前の安全確認や歴史的遺物の保全調査などにも利用され、安全面での安心感が高い方法です。
レイリー波探査による地盤評価
レイリー波探査は、地表面に振動を与え、その際に発生する表面波(レイリー波)の伝播速度を複数の受振器で測ることで、地中のせん断波速度分布を推定する手法です。地盤の硬さや空洞、不同沈下リスクを面的に把握できるため、住宅基礎の設計や道路・橋脚の耐震評価に用いられます。通常は深度30m程度まで評価可能で、地盤改良後のチェックにも便利です。
ボアホールレーダー/高密度表面波探査の応用
ボアホールレーダーは、ボーリング孔内に専用アンテナを挿入して周囲を断面像でスキャンする方法です。基礎杭の根入れ深度や地下構造の詳細な三次元分布を高精度に把握できます。一方、高密度表面波探査(MASW)は、等間隔に多点設置した受振器で同時にデータを取り、面状のせん断波分布を得る技術です。地質構造をより細やかに可視化でき、広い現場でも均質な結果を得られるのが強みです。
ボーリング調査・試掘による直接確認
最も確実なのはボーリング調査や試掘による直接観察です。ハンマードリルで小孔をあけ、ファイバースコープで内部を撮影したり、試料を採取したりしながら、非破壊探査では届かない細部まで確認します。コストや手間は増えますが、他の手法で得られた結果の検証や、非金属・複雑地層の把握には欠かせません。
手法選定のための比較ポイント
深度レンジ・解像度比較
探査方法によって、掘削深度と検出できる障害物の大きさに特徴があります。GPRは周波数を変えることで深度と分解能を調整でき、900MHz帯で数十センチ単位の精度、300MHz帯で数メートル深く探査可能です。EMIは金属に特化し、深度数十センチから数メートルの範囲を20〜30cm程度の解像度で追跡できます。磁気探査は0.5〜1mほどの浅い層に強みがあり、MASWは地盤全体の硬軟を深さ数十メートルまで把握できるため、液状化対策や地盤支持力評価に適しています。ボアホールレーダーはボーリング孔の深度に応じて探査範囲が広がり、数十メートル先まで掘削不要で調べられる点が魅力です。
土質・環境条件への適応性
GPRは砂質土や凍結地盤で安定した探査ができる一方、粘土質や含水率の高い地盤では電磁波が減衰しやすくなります。EMIは土質による影響が少ないため、雨で湿った土地や舗装下でも比較的安定した測定が可能ですが、非金属には反応しません。磁気探査は舗装越えも得意ですが、地形の起伏や磁性鉱物の多い地盤ではバックグラウンドノイズが増大することがあります。MASWは発震条件や表面の凹凸、交通振動などの影響を受けやすいため、設置とタイミングに注意が必要です。
コスト感と作業スピード
GPRは機器レンタルや解析費用を含めると1日の調査で数十万円規模になることがありますが、車載型機器を使えば高速道路下など広い範囲を短時間でカバーでき、施工前の効率が高まります。EMIは数千円~数万円程度のレンタルで導入でき、歩行速度で測定できるため狭い場所や段差のある現場でも素早く調査可能です。MASWは受振器の設置と解析に専門技術者が必要なため、やや高コストですが、一度の調査で広いエリアの地盤剛性評価が得られます。ボアホールレーダーはボーリング費用を要しますが、深度精度と詳細さを優先する場合に選択されます。
機器選定とキャリブレーション
GPRでは高解像度が必要な管路調査に800MHz帯を使い、深部探査には300MHz帯を組み合わせるのが一般的です。EMIでは現地で校正を行い、ループ法か外部コイル法かを作業環境に応じて使い分けます。磁気探査機器は公的機関の校正標準を用いてドリフト補正を実施し、MASWでは使用するジオフォンの周波数特性を事前確認したうえで同一ロットを揃えることでデータのばらつきを抑えます。
調査実施のフローと留意点
事前調査・現地調整の進め方
調査前にはまず過去の地図や工事履歴を確認し、ヒアリングで想定位置を絞り込みます。次に道路占用許可など必要な手続きを済ませ、現地下見で測線やアンテナ走行ルートを決定します。この段階で適切な調査範囲と測定条件を確定しておくことで、現場での手戻りを減らし、安全かつ効率的に作業を進めることができます。
データ取得から解析までの手順
現場では測線をマーキングし、GPRやEMI、磁気探査の機器を所定間隔で走査します。GPRは車載または手押しで走行しながら数センチ間隔でスキャンし、EMIや磁気探査も同様に測線に沿って歩測します。取得したデータは現場で簡易フィルタリングをかけてノイズを抑え、帰社後に専門ソフトで断面像や等高線マップを作成します。最終レポートでは測線図や解析結果、検出箇所の位置・深度を図示し、施工チームへ分かりやすく共有します。
ノイズ対策と信号処理ポイント
地下探査では舗装材や地下水、近隣設備からの反射がノイズ源となります。GPRでは帯域制限フィルタや時間窓フィルタを使い、主反射だけを強調します。磁気探査は差動測定で地球磁場変動を除去し、EMIは多周波測定により偽信号を抑えます。特に車載調査では走行速度の変動によるドップラー歪みを補正する処理が有効で、精度を維持しながらスピーディにデータ取得できます。
報告書作成時の押さえるべき項目
報告書には測線図、機器仕様、測定条件(周波数、測線間隔など)を明記し、代表的な断面図と検出位置・深度を図示します。併用した手法の結果を比較したデータや、試掘・ボーリングによる確認結果を合わせて掲載すると、調査精度の担保につながります。また、工事設計への反映ポイントやリスク低減策も提案し、施工計画書としてそのまま使えるレベルの完成度を目指しましょう。
まとめ
地中レーダー探査は高解像度の断面図取得に優れ、電磁誘導法は金属管の迅速検出、磁気探査は鋼製構造物の把握に適しています。MASWは地盤全体の硬軟を把握でき、ボアホールレーダーやボーリング調査は深部・精密探査に欠かせません。現場の目的や予算、環境条件に合わせて複数の手法を組み合わせることが最良の結果を生みます。
まずは手軽に使える地中レーダー探査(GPR)を試してみてはいかがでしょうか。専門的な知識がなくても操作しやすい機器が増えており、比較的短期間で地中の様子を可視化できます。